行政書士の開業準備やリニューアルを考えている方の中には、ロゴについて、
どんなデザインが適しているの?
どうやって作ればいいの?
ロゴってそもそも必要なの?
と、考える方も多いのではないでしょうか。
この記事では、「ロゴの効果や心理的影響」「デザインの考え方や作成のコツ」「完成後の活かし方」について現役の行政書士が詳しく解説します。
ロゴを作成して事務所の信頼感を上げたい!という方は、ぜひ参考にしてください。
行政書士にロゴって必要?

ロゴで信頼感・印象が変わる理由
行政書士事務所の開業時に、「ロゴを作るべきかどうか」は多くの方が悩むポイントです。
結論から言うと、ロゴには次のような効果が期待できるため、作るべきだと思います。
| ロゴの効果 | 詳細 |
|---|---|
| 信頼度の向上 | しっかりした事務所という箔がつき、信頼度が上がる ・名刺や封筒:ロゴ入り>無地 ・WEBサイト:事務所ロゴ>何もなし |
| 差別化 | 他事務所との違いが明確になり、差別化ができる |
| 印象に残る | 視覚情報は言葉以上に記憶に残りやすく、覚えてもらいやすい |
ロゴは、行政書士の“顔”
ロゴがあることで、士業に求められる「安心感」「誠実さ」「専門性」を”アピールする”ことができます。
ロゴが与える第一印象の心理的効果
ロゴは、“第一印象”に大きく影響します。
なぜかというと、視覚から得た情報は、たった数秒で「信頼できそう」「真面目そう」という見た人の感情を動かす力があるからです。
心理学的には、「色」「形」「余白のバランス」などが感情に作用すると言われています。
例えば、「色」に関しては、
- 青色 → 誠実・安心
- 緑色 → 中立・調和
- 赤色 → 情熱・やる気
を感じさせることができるのです。
その効果を意図的に狙い、「誠実感・信頼感」をいかに視覚で演出できるかが大きなカギとなるでしょう。
行政書士のロゴに必要なデザインの考え方

行政書士のロゴには品格があるべき
一般的に、士業に求められる要素は、「知識力」「対話能力」「正確性」「中立性」「責任感」などです。
並べてみると世間的な理想がやや高い気はしますが、一言で表すなら、いわゆる「品格」というものです。
具体的には、
- シンプルな構成(図形、文字)
- 読みやすいフォント(明朝体、ゴシック体)
- 寒色系(青・紺・グレー)を中心とした落ち着いた色合い
を用いたロゴのデザインが世間のイメージに近いと言えます。
逆に言えば、過度な装飾や派手すぎるデザインは好まれにくいでしょう。
ちなみに、「コスモス(行政書士会の象徴)」をモチーフにしたロゴをよく見かけますが、私は他の事務所と被ることを避けるため、コスモスは使っていません。
避けたいデザインとやりがちな失敗例
行政書士に限らず、ロゴ制作でありがちな失敗例はいくつか挙げられます。
上記の例について、明確な意図があり、あえて採用しているなら良いですが、基本的には避けた方がいいと思います。
また、ロゴの使用場所(名刺、サイトアイコン、封筒など)に応じて、拡大・縮小したときの見やすさも考える必要があります。
作っている時は、「とてもいい…!」と思っていても、実際は使用しづらいということがあるかもしれません。
様々なシチュエーションで使用できるよう、形のパターン(正方形、長方形、円の場合など)も考慮するといいでしょう。
色・フォントが与える印象と選び方
「人間が視覚から得る情報の約8割は色によるもの」と言われています。
つまり、色の選び方次第で印象が大きく変わります。
次の表を参考に、与えたい印象から逆算して色を選んでみましょう。
| 色 | プラスな印象 | マイナスな印象 |
|---|---|---|
| 赤 | 情熱、行動力、やる気、 エネルギー、興奮、生命力 | 暴力的、怒り |
| 橙 | 元気、健康的、暖かい、活発、 友好的、カジュアル、明るい | |
| 黄 | 元気、活動的、軽快、希望、 素直、友好的、陽気、明るい | 注目、緊張、危険 |
| 緑 | リラックス、癒し、調和、 安定、若々しい、エコロジー | |
| 青 | 知的、冷静、気品、信頼感、 真面目、誠実、爽快感 | 冷たさ、悲しさ、寂しさ |
| 紫 | 上品、高貴、神秘的、優雅、 魅力的、妖しい、神秘 | 近寄りがたい、不気味 |
| 白 | 純粋、清潔、爽快感、 神聖、平和、正義 | 無気力、空虚 |
| 黒 | 高級、重厚、威厳、 優雅、洗練 | 絶望、不安、恐怖 |
| フォント | 印象 |
|---|---|
| 明朝体 | 伝統・格式・信頼 |
| ゴシック体 | 現代的・読みやすい・安定感 |
| 手書き風 | 親しみやすさ |
また、色の選び方は、取扱い業務を意識してみることもオススメです。
例えば、
- 許認可業務
- 紺色や濃灰色:誠実さや信頼感
- 遺言・相続業務
- 緑色や茶色などの優しい色合い:家族の温かみや安心感
という演出をすることができます。
他には、「あなたの性格を表す色」をテーマにして選ぶことも良いと思います。
色やフォントが与える印象を利用することで、事務所のロゴがしっかりと意味のあるものになります。
効果的なロゴの作成方法
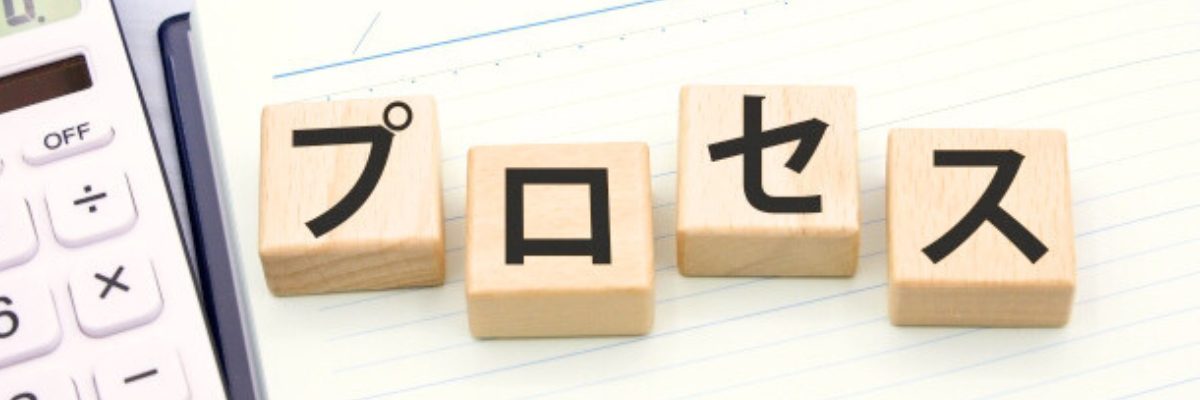
ロゴ制作に正解はありませんが、次のプロセスを辿ることで、納得のいくデザインに近づけます。
- 事務所イメージを言語化
- 参考デザインの収集
- 色・フォントの方向性を決める
- 簡単なスケッチやイメージ図を作成
- デザイン作成ツールで試作
- 使用場面ごとの検証→完成
- 難しいならプロに頼む
① 事務所イメージを言語化
まずは、以下の表のように「どんな事務所にしたいか」を言語化してみましょう。
そして、その言葉から連想されるイメージをどんどん膨らませて、ロゴデザインの要素となる候補を挙げていきます。
| プロセス | 言語化とデザイン要素の例 |
|---|---|
| どんな事務所にしたい? | 人との繋がりを大切にする事務所 |
| ↓ | ↓ |
| 連想される キーワードは? | 繋がり、共感、絆、温かさ 連携、協調、対話、心地よさ |
| ↓ | ↓ |
| 連想される 色のイメージは? | 緑(共生、調和) オレンジ(温かみ、親しみやすさ) ベージュ(自然、安心感) |
| 形のイメージは? | 円(繋がり、調和)、曲線 重なり合う要素、手と手を取り合う 複数人がいるシルエット |
| モチーフのイメージは? | 葉(成長、共生)、波紋(広がり) 糸(繋がり)、橋(架け橋) |
このようなプロセスをしっかりと辿ることで、ロゴデザインの”軸”が生まれ、コンセプトのブレも防ぐことができます。
② 参考デザインの収集
次に、他の士業事務所や企業ロゴを見て、気になるものをピックアップしていきましょう。
何事にも言えますが、インプットなしに良質なアウトプットはありません。
もちろん、「かっこいい」「真面目そう」など、直感的な印象でOKです。
デザインをたくさん知ることは重要ですし、自分の好みや方向性を整理する上でも効果があります。
さらに、他の行政書士事務所のロゴを見れば、デザインの傾向に気づき、発想のヒントを得ることもできます。
また、有名企業のロゴも参考になります。

例えば、Googleのロゴは、色の三原色「赤、青、黄」(=基本)に補色「緑」(=意外性)を加えることで、「Googleはルールや常識に従わないという哲学の想起」を表しているそうです。
③ 色・フォントの方向性を決める
先述の「色・フォントが与える印象と選び方」を参考に、方向性を決めましょう。
ちなみに、私が色選びでよく使うツールは、Adobe Colorのカラーホイールです。
ベースカラーに対する色(類似色、補色、シェードなど)を自動で生成してくれます。
無料で使えてかなり便利なのですが、色に関する知識をつけなければやや難解かもしれないです。
④ 簡単なスケッチやイメージ図を作成
次に、手順①で書き出した要素を基に、デザイン案をいくつか紙で書いてみましょう。
ざっくりでいいので、シンボルマークや文字の配置、色のバランスなどをラフに描いてみることで、デザインの方向性が整理されていきます。
⑤ デザイン作成ツールで試作
次は、実際にロゴをデザインツールで作成していきます。
Canva、PowerPointなら、無料でテンプレートも多く、デザイン初心者にも扱いやすいと思います。
ただし、差別化という点では限界があるため、テンプレートはあくまでデザインの参考として捉えましょう。
また、デザインが一つできてもそこで手を止めずに、色やフォント、空白や配置が異なるパターンを他にも考えてみることがデザインを仕上げるコツです。
少しの違いで大きく印象が変わることもあるため、何パターンも試して最良のデザインを見つけていきましょう。
⑥ 使用場面ごとの検証→完成
できあがったロゴ案を、実際に使用する場面で想定・検証してみましょう。
名刺に印刷しても潰れないか?
WEBサイトのヘッダーやアイコンでも見やすいか?
封筒やチラシなどに入れても違和感はないか?
いろいろなサイズや背景に置いてみることで、「本当に使えるロゴかどうか」がわかってきます。
⑦ 難しいならプロに頼む
「どうしても納得のいくデザインにならない…。」と悩むなら、いっそのことプロにお任せするのも手です。
ココナラでは、各デザイナーの制作事例を見れるため、自分に合ったデザイナーを探すことができます。
ちなみに別件ですが、私が過去にココナラを利用した時は、レビュー数が多い方へお願いしたので、やり取りも手慣れていてスムーズでした。
もしロゴデザインを発注するなら、事務所イメージの言語化をしておくことで、やり取りがスムーズに進み、納得のいくロゴに仕上がるはずです。
ロゴ完成後の使い方と展開

ロゴは名刺・HP・書類で活かす
完成したロゴは、行政書士事務所のあらゆる媒体で活用できます。
- 名刺・封筒:ロゴ入りで信頼感アップ
- WEBサイト:ヘッダーやファビコン
- チラシ・資料:事務所ブランドとして定着
個人的に、名刺・封筒・チラシなどは、オリジナルデザインの作成から印刷までワンストップで行えるビズハウズがオススメです。
また、WEBサイトのファビコンやサイトアイコンというのは、以下の赤枠を指します。
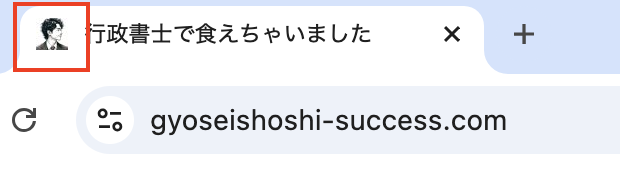
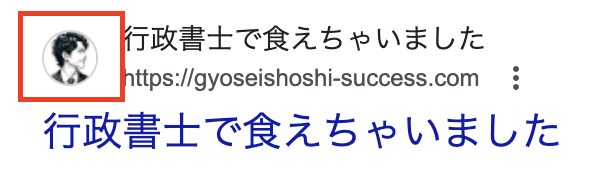
色の統一でブランド力を上げる
ロゴに使われている色は、事務所のイメージカラーとしても利用できます。
つまり、事務所に関するすべての色を統一させることで、ブランディングにも活かすことできます。
例えば、ロゴで用いた基本色(プライマリーカラー)をWEBサイトのデザインに取り入れることで、より統一感を出すことができます。
さらに、問合せボタンなどの目立たせたい箇所に補色(セカンダリカラー)を使うことで、統一感を損なわずに強調させることもできます。
また、名刺や封筒、クリアファイルといった印刷物にも事務所のイメージカラーを取り入れれば、ブランディングを意識している「しっかりした事務所」という印象を残すことができるでしょう。
こうした細かな配慮やちょっとした違いが、行政書士事務所としてのブランド力をじわじわと高めていきます。
最後に ロゴは行政書士の顔
以上、行政書士事務所のロゴについて解説しました。
| ロゴの効果 | 詳細 |
|---|---|
| 信頼度の向上 | しっかりした事務所という箔がつき、信頼度が上がる ・名刺や封筒:ロゴ入り>無地 ・WEBサイト:事務所ロゴ>何もなし |
| 差別化 | 他事務所との違いが明確になり、差別化ができる |
| 印象に残る | 視覚情報は言葉以上に記憶に残りやすく、覚えてもらいやすい |
- シンプルな構成(図形、文字)
- 読みやすいフォント(明朝体、ゴシック体)
- 寒色系(青・紺・グレー)を中心とした落ち着いた色合い
- 事務所イメージを言語化
- 参考デザインの収集
- 色・フォントの方向性を決める
- 簡単なスケッチやイメージ図を作成
- デザイン作成ツールで試作
- 使用場面ごとの検証→完成
ロゴはまさに「行政書士の顔」として、あなたの誠実さや信頼感を視覚で伝えられる強力なツールです。
名刺やWEBサイトにロゴがあるだけで、初対面のお客様に安心感を与えられ、「きちんとした事務所」という印象を自然と持ってもらえることもあります。
信頼されるロゴを作りたいなら、「〇〇な事務所にするぞ!」という具体的なコンセプトを基に、色やフォントなどを決めて丁寧にメッセージ性を込めましょう。
そこに特別なデザインスキルは必要なく、大事なことは「どんな行政書士になりたいか?」という自分自身へのシンプルな問いかけです。
そうして作り上げたロゴには、我が子のような愛着が生まれ、かけがえのないものになるでしょう。


